「事業再構築補助金の申請代行支援サービスの選び方のポイント」はこちら
※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます
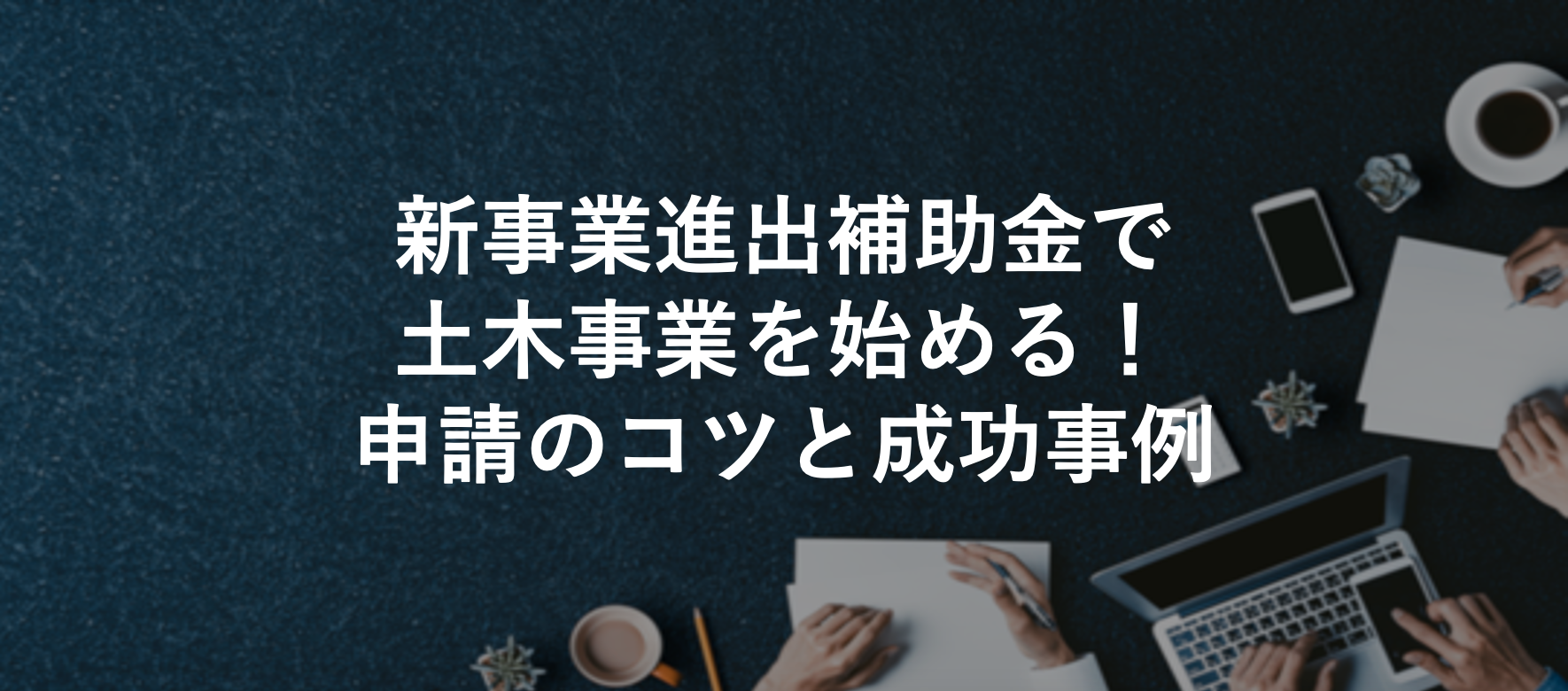
土木事業への新規参入や事業拡大を考えている方にとって、資金調達は大きな課題です。この課題を解決する手段の一つとして、国が提供する「中小企業新事業進出補助金(以下、新事業進出補助金)」の活用が有効です。
本記事では、新事業進出補助金の概要から、土木事業における活用方法、申請のコツ、成功事例、申請後の流れまでを網羅的に解説します。
この記事を読むことで、新事業進出補助金が土木事業にどのように活用できるのか、どのようなメリットがあるのかを理解し、採択率を高めるための具体的な戦略を学ぶことができます。実際に補助金を受けて成功した企業の事例も紹介するので、より実践的な知識を得られるでしょう。
ぜひ本記事を参考に新事業進出補助金を活用して、土木事業を成功させてみてください!


監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
新事業進出補助金は、中小企業庁が実施する補助金制度で、革新的な新事業に挑戦する中小企業・小規模事業者を支援することを目的としています。新規性、独創性のある事業を展開することで、地域経済の活性化や雇用の創出を促進する狙いがあります。
補助対象となる経費は多岐にわたります。この補助金を活用することで、土木関連事業立ち上げに伴う初期投資の負担を軽減し、円滑な事業展開を実現することができるでしょう。
新事業進出補助金とは?土木事業に活用してみよう
新事業進出補助金は、事業計画に基づいて補助金を交付する制度です。審査を通過するためには、事業の成長性や収益性、地域貢献度などを明確に示す必要があります。
補助率は、経費の1/2で、補助上限額は以下の通りです。
| 従業員数 | 補助上限金額 | 補助率 |
| 従業員数20人以下 | 750万円〜2,500万円(3,000万円) | 1/2 |
| 従業員数21~50人 | 750万円〜4,000万円(5,000万円) | |
| 従業員数51~100人 | 750万円〜5,500万円(7,000万円) | |
| 従業員数101人以上 | 750万円〜7,000万円(9,000万円) |
※賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助上限額を適用
補助金は補助事業完了後に払われるので注意しましょう。
新事業進出補助金の対象となる事業は、新規性、独創性があり、成長性が見込まれる事業です。具体的には、新製品・新サービスの開発、新たな販路開拓、生産プロセスの革新などが挙げられます。また、地域経済の活性化や雇用の創出に貢献する事業も高く評価されます。単なる設備の更新や既存事業の規模拡大は対象外となるため、事業計画の策定には注意が必要です。
既存事業の単なる規模拡大や設備の更新、ギャンブル関連事業、風俗営業などは補助対象外です。また、公序良俗に反する事業や政治活動、宗教活動なども対象外となります。さらに、既に他の補助金を受けている事業も対象外となる場合があります。補助対象となる事業かどうか不明な場合は、事前に事務局に相談することをお勧めします。
土木事業は、社会インフラの整備や災害復旧など、私たちの生活基盤を支える重要な役割を担っています。
しかし、新規事業への投資には多額の費用が必要となるため、資金調達が大きな課題となるケースも少なくありません。そこで、ぜひ新事業進出補助金を活用し、土木事業における新たな取り組みを促進し、地域経済の活性化や雇用の創出に繋げていきましょう。
土木事業における新事業進出補助金の活用
新事業進出補助金を活用することで、以下のようなメリットが期待できます。
新事業進出補助金の対象となる土木事業は多岐に渡ります。以下に具体的な例を挙げ、それぞれの内容と補助金の活用ポイントを解説します。
ただし、あくまでも本補助金は新たに土木事業を始める方のみが活用できるものであることに注意しましょう。既存事業として土木事業をすでに行なっている方は、土木事業に本補助金を使うことはできません。
道路新設、拡幅、舗装工事など、地域住民の生活利便性向上や物流効率化に繋がる道路工事が対象となります。例えば、老朽化した道路の改修や、交通渋滞の緩和を目的としたバイパス建設などが該当します。補助金を活用することで、工事費用の一部を賄い、円滑な事業推進が可能となるでしょう。
老朽化した橋梁の架け替えや耐震補強工事などが対象となります。地域住民の安全確保や災害時の緊急輸送路の確保に繋がる重要な事業です。補助金を活用することで、高額な工事費用への負担を軽減できます。
堤防整備や河川改修工事など、洪水被害の軽減や水資源の確保に繋がる河川工事が対象となります。近年頻発する豪雨災害への対策として、重要性が高まっています。補助金を活用することで、多額の費用を要する河川工事の推進を支援します。
水道管の更新や下水道整備など、衛生環境の改善や生活用水の安定供給に繋がる上下水道工事が対象となります。老朽化した水道管の更新は、漏水防止や水質保全の観点からも重要です。補助金を活用することで、これらの工事を効率的に進めることができます。
上記以外にも、トンネル工事や港湾工事など、様々な土木事業が補助金の対象となります。それぞれの事業内容に合わせて、補助金を効果的に活用することで、事業の成功に繋げましょう。事業計画の策定にあたっては、地域のニーズや課題を的確に捉え、実現可能性の高い計画を立てることが重要です。また、専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な補助金活用が可能になるでしょう。
上記以外にも、トンネル工事や港湾工事など、様々な土木事業が補助金の対象となります。それぞれの事業内容に合わせて、補助金を効果的に活用することで、事業の成功に繋げましょう。事業計画の策定にあたっては、地域のニーズや課題を的確に捉え、実現可能性の高い計画を立てることが重要です。また、専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な補助金活用が可能になるでしょう。
新事業進出補助金の第2回公募が令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00まで実施されています。申請は、事業計画の策定から申請書類の提出、審査、そして交付決定までの一連の手続きが必要です。スムーズな申請のために、以下の手順と必要書類、注意点を確認しましょう。
土木事業で新事業進出補助金に申請する方法
申請に必要な書類は多岐に渡ります。事前に準備をしっかりと行い、漏れのないようにしましょう。
主な書類は以下の通りです。
申請から交付決定までの流れと、大まかなスケジュールは以下の通りです。
スケジュールは補助金の種類によって異なりますが、一般的には申請から交付決定まで数ヶ月かかることが多いです。余裕を持って準備を進めましょう。
中小企業者、特定の中小企業者等、特定事業者の一部が申請資格の対象となります。建設業の場合、資本金3億円以下かつ常勤従業員数300人以下の会社または個人が中小企業者として該当します。また、補助金の種類によっては、特定の業種や地域が対象となる場合もあります。
補助対象となる経費は、機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費です。それぞれの経費にルールが設定される可能性もあるので、よく確認してから申請しましょう。機械装置・システム構築費または建物費のいずれかは必須となります。
申請後に事業計画などを変更する場合は、速やかに補助金事務局に連絡し、承認を得る必要があります。無断で変更すると、補助金の交付が取り消されてしまうかもしれません。
新事業進出補助金の採択を目指す上で、綿密な事業計画書の作成と審査ポイントの理解は不可欠です。計画性と実現可能性を効果的にアピールすることで、補助金獲得の可能性を高めましょう。
土木業で新事業進出補助金に申請するコツ
事業計画書は、あなたの事業構想を審査員に伝えるための重要なツールです。明確かつ説得力のある記述を心がけましょう。
事業の目的を具体的に記述し、その目的を達成するためにどのような事業を行うのかを明確に説明します。新規性や独自性、地域貢献など、事業の強みを強調することが重要です。既存事業との差別化ポイントや、地域経済への波及効果についても言及することで、審査員の関心を高めることができます。
ターゲット市場の規模や成長性、競合他社の状況などを分析し、事業の優位性や将来性を客観的なデータに基づいて示す必要があります。市場調査データや統計資料などを活用し、説得力のある分析を行いましょう。SWOT分析などを用いて、事業の強み・弱み・機会・脅威を明確にすることも有効です。
事業にかかる費用と見込まれる収益を具体的に示し、事業の収益性や持続可能性を明らかにします。補助金以外の資金調達方法についても説明し、財務計画の健全性をアピールしましょう。3年間の収支計画を作成し、売上高、経費、利益などを詳細に記載することが求められます。初期投資額や運転資金、資金回収の見込みなども具体的に示すことが重要です。
新事業進出補助金の審査では、以下のポイントが重視されます。事業計画書を作成する際には、これらのポイントを意識することが重要です。
| 審査項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象事業としての適格性 | 公募要領に記載する補助対象者、補助対象事業の要件を満たしているか。補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。 |
| 新規事業の新市場性・高付加価値性 | 補助事業で取り組む新規事業により製造等する新製品等のジャンル・分野の、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。または、同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。 |
| 新規事業の有望度 | 補助事業で取り組む新規事業が、継続的に売上・利益を確保できるだけの市場規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。競合分析を実施した上で、競合他社と比較して自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。 |
| 事業の実現可能性 | 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。 |
| 公的補助の必要性 | 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価されます。補助事業として費用対効果が高いか。先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。 |
| 政策面 | 経済社会の変化に伴い、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るか。地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか。 |
補助金の採択率を上げるためには、以下の戦略が有効です。
これらのコツを踏まえ、しっかりと準備を進めることで、新事業進出補助金の採択に大きく近づけるはずです。ぜひ、積極的に活用し、事業の成功につなげてください。
補助金を利用して土木事業を成功させた企業の事例を紹介します。これらの事例を確認し、事業計画の立案や申請書の書き方の参考にしたり新事業進出補助金活用の可能性を広げてみたりしてください。
土木事業で補助金を活用した成功事例
株式会社Aは、補助金を活用し、ICT技術を駆使したスマート建設を導入しました。従来の施工方法では困難だった高精度な施工管理を実現し、生産性の大幅な向上に成功しました。具体的には、3Dモデルを活用した施工計画や、ドローンによる測量、自動化施工機械の導入などを行い、工期短縮とコスト削減を達成しました。
建設業界全体の高齢化と人手不足が深刻化する中、生産性向上は喫緊の課題です。Aは、この課題解決のため、補助金を利用してスマート建設導入による生産性向上を目指しました。本事業では、山岳トンネル工事において、ICT技術を活用した掘削機ガイダンスシステム、自動追尾型測量システムなどを導入し、施工の効率化と安全性の向上を図りました。
| 項目 | 成果 |
|---|---|
| 工期 | 20%短縮 |
| コスト | 15%削減 |
| 安全性 | ヒューマンエラーによる事故発生率を80%削減 |
株式会社Bは、環境問題への意識の高まりを受け、補助金を活用して環境負荷低減型建設資材の開発に取り組みました。従来のコンクリートに比べてCO2排出量を大幅に削減できる新素材を開発し、環境に配慮した土木工事を実現しました。
持続可能な社会の実現に向けて、建設業界における環境負荷低減は重要な課題です。Bは、この課題解決のため、補助金を利用して環境負荷低減型建設資材の開発を行いました。本事業では、産業副産物を利用したリサイクルコンクリートの開発と、CO2吸収能力を持つコンクリートの開発を行い、環境負荷低減に貢献しました。
| 項目 | 成果 |
|---|---|
| CO2排出量 | 従来比30%削減 |
| 産業副産物利用率 | 50%向上 |
C株式会社は、自然災害の増加を背景に、補助金を活用して防災・減災技術の開発を行いました。地震や津波に強い構造物の設計技術を開発し、地域社会の安全・安心に貢献しました。
近年、自然災害の激甚化・頻発化が社会問題となっています。Cは、この課題解決のため、補助金を利用して防災・減災技術の開発を行いました。本事業では、津波による建物の浮き上がりを防ぐ技術や、液状化対策技術の開発を行い、災害に強い地域づくりに貢献しました。
| 項目 | 成果 |
|---|---|
| 耐震性能 | 震度7クラスの地震にも耐えられる構造物を開発 |
| 津波対策 | 津波による建物の被害を最小限に抑える技術を開発 |
これらの事例は、補助金が土木事業の進化や地域社会への貢献に役立っていることを示しています。補助金を活用することで、企業は新たな技術開発や事業展開に挑戦することができ、持続可能な社会の実現に貢献できるのです。ぜひ、これらの成功事例を参考に、新事業進出補助金の活用を検討してみてください。
新事業進出補助金の交付決定を受けた後には、速やかに事業に着手し、補助事業を適切に実施していく必要があります。また、補助金は後払いであるため、適切な手続きと実績報告が求められます。ここでは、交付決定から実績報告までの流れ、そして事業実施中の注意点について詳しく解説します。
新事業進出補助金に土木事業で申請した後の流れ
補助金交付決定通知を受け取ったら、まずは交付決定の内容を確認し、間違いがないかを確認しましょう。記載内容に誤りがあった場合は、速やかに事務局に連絡する必要があります。その後、補助事業に着手することができます。ただし、補助金の交付決定前に事業に着手してしまうと、補助対象外となる可能性があるので注意が必要です。
また、補助金交付申請時に提出した事業計画の内容に変更が生じる場合は、事前に事務局へ変更承認申請を提出する必要があります。軽微な変更であれば手続きは簡略化されますが、事業内容や補助金額に大きな変更が生じる場合は、改めて審査が行われることもあります。変更なく事業を進められるよう、計画段階から綿密な準備を行うことが重要です。
事業実施中は、補助金の交付目的に沿って事業を遂行することが重要です。また、経理処理を適切に行い、証拠書類を保管しておく必要があります。補助対象経費と補助対象外経費を明確に区分し、領収書や請求書などの証拠書類を整理・保管しておきましょう。不正な経理処理が発覚した場合、補助金の返還を求められるだけでなく、今後の補助金申請にも影響が出かねません。
また、定期的に事業の進捗状況を確認し、計画通りに進んでいるか、問題が発生していないかなどをチェックすることも重要です。進捗状況に遅れが生じている場合や、予期せぬ問題が発生した場合は、速やかに事務局に相談し、適切な対応を取りましょう。
事業完了後は、実績報告書を作成し、事務局に提出する必要があります。実績報告書には、事業の実施状況や成果、経費の執行状況などを詳細に記載する必要があります。
また、領収書や請求書などの証拠書類も添付する必要があります。実績報告書の内容に基づいて、補助金の額が確定します。報告書の記載内容に誤りがあったり、証拠書類が不足していたりすると、補助金の支払いが遅れたり、減額されたりする可能性があります。提出期限までに正確な実績報告書を作成し、必要な書類を揃えて提出することが重要です。以下に、実績報告書に一般的に含まれる内容をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業概要 | 実施した事業の概要を記載 |
| 事業実施期間 | 事業の開始日と終了日を記載 |
| 事業の成果 | 事業によって得られた成果を定量的に記載 |
| 経費執行状況 | 補助金の使用状況を詳細に記載(内訳を含む) |
| 添付書類 | 領収書、請求書、写真等、事業実施を証明する書類 |
実績報告書の提出後、事務局による審査が行われます。審査の結果、内容に不備がある場合は、修正を求められることがあります。また、現地調査が行われる場合もあります。審査を通過すると、補助金が交付されます。補助金は、指定された口座に振り込まれます。
実際に新事業進出補助金に申請するとなると、かなり時間も手間もがかかります。採択されるためには事業進出補助金は明確に丁寧に作成する必要があり、さらに不備のない書類提出も欠かせません。自社だけで申請作業をするのはかなり骨が折れてしまうでしょう。
そんな時便利なのが申請支援サービスを利用することです。株式会社補助金プラスでは、新事業進出補助金をはじめ様々な補助金の申請支援サービスを行っています。お客様の状況、今後の展望を丁寧にヒアリングし、採択に向けた準備を行います。
これから新事業進出補助金に申請しようと考えている方は、ぜひ株式会社補助金プラスに一度お問い合わせください。
この記事では、新事業進出補助金を活用して土木事業を始めるためのポイントを解説しました。新事業進出補助金は、新規性や成長性のある事業に対して資金面での支援を行う制度であり、土木事業においても活用することで、初期投資の負担軽減や事業拡大を促進することができます。補助対象となる土木事業は、道路工事、橋梁工事、河川工事、上下水道工事など多岐に渡ります。
申請にあたっては、事業計画書の綿密な作成が重要です。事業の目的や内容、市場分析、競合分析、収支計画などを明確に記載し、審査員に事業の将来性や実現可能性を理解してもらう必要があります。採択率を上げるためには、地域のニーズに合致した事業内容にする、十分な市場調査を行う、実現可能な収支計画を立てるなどの戦略が有効です。
株式会社A社の道路舗装工事や株式会社B社の橋梁耐震補強工事の成功事例からもわかるように、綿密な計画と準備によって、補助金の活用は土木事業の成功に大きく貢献します。補助金交付決定後も、事業実施中の注意点や実績報告書の提出など、適切な手続きを行うことが重要です。この記事を参考に、新事業進出補助金を活用し、土木事業の成功を目指しましょう。
