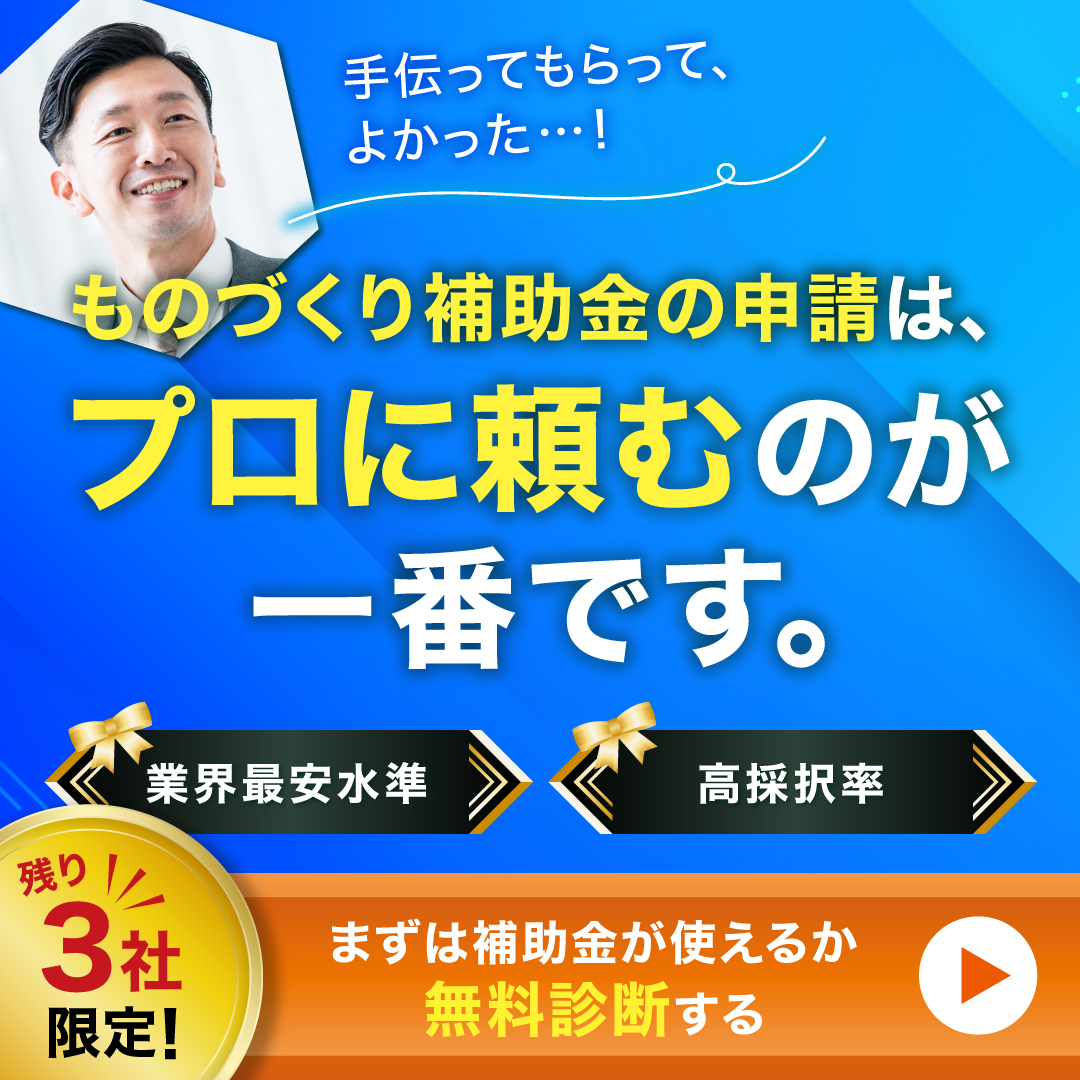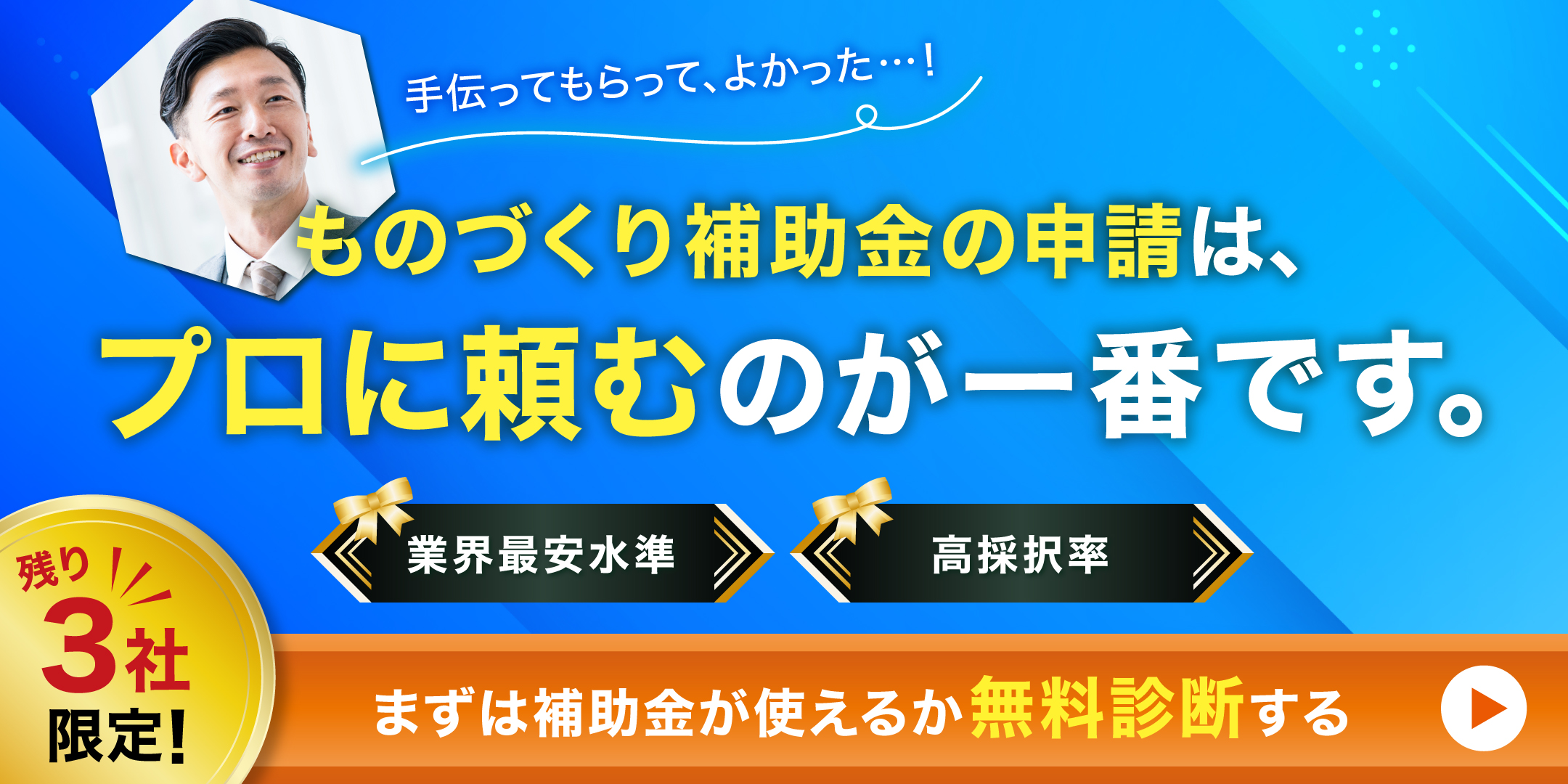【2024.2】ものづくり補助金での補助事業期間は延長可能?延長方法についても解説!

「ものづくり補助金」は、中小企業や小規模事業者の生産性向上のための設備投資等の事業経費を国が支援するという人気の補助金です。ただ、「ものづくり補助金の補助事業期間は延長することは可能なのか」と、疑問を抱く方は多いでしょう。
この記事では、補助事業期間を延長させる方法について解説していきます。
- ものづくり補助金の概要が理解できる
- ものづくり補助金の補助事業期間の延長の可否がわかる

ものづくり補助金とは?
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業等に交付される補助金の1つです。
企業の生産性向上に資する革新的なサービスや試作品の開発、生産製造におけるコストの削減やプロセス改善を行うための設備投資等の事業経費を国が支援する制度です。
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等など、昨今の労働環境の相次ぐ制度改革に対応する事業にも活用することができます。
ものづくり補助金とは?
ものづくり補助金はどんな補助金?
ものづくり補助金は、中小企業の総合的な経営力向上を目的としている補助金制度です。
これまでにものづくり補助金は、のべ7万社以上の中小企業・小規模事業者の「革新的サービス」・「試作品開発」・「生産プロセス」の改善等を行うための設備投資などに活用されてきました。
例えば、AIやロボットをはじめとする革新的なサービスや、ドローンやCADシステムを利用した生産プロセスの改善を行った事業です。
他にも、最新機械を導入し生産製造におけるコストの削減や、プロセス改善を行う設備投資の事業経費にものづくり補助金を活用した採択事例が多く見受けられます。
交付された補助金は原則として返済する必要はなく、銀行融資のように担保・保証人が求められることもありません。よってものづくり補助金は申請に審査がありますが、応募件数の多い人気の補助金です。
ものづくり補助金の対象事業者は?
ものづくり補助金の対象事業者は、中小企業や個人事業主、特定非営利活動法人、社会福祉法人が対象となります。日本の全企業数の99%以上が中小企業なのでものづくり補助金の門戸はかなり開かれているといえるでしょう。
また、第10次公募(令和4年2月中旬)から、ものづくり補助金の申請の対象企業範囲の見直し・拡充が行われ、「特定事業者」も対象となりました。
「特定事業者」とは、資本金10億円未満の企業です。中小企業にとどまらず、成長途上にある中堅企業への支援も拡大することで、日本企業全体の基盤を強固にしていく国側の狙いがみえます。
ものづくり補助金の申請方法は?
ものづくり補助金の申請は、「公募期間内に事業計画書を電子申請する」という流れで行います。
ものづくり補助金の電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要で、取得には3週間ほどかかることから早めにアカウントを作成しましょう。
取得したGビズIDでものづくり補助金の電子申請システムにログインし、事業計画書の入力や必要書類のアップロードや添付作業を行い、送信することでものづくり補助金の申請は完了です。
補助金の申請後、事業計画書等の審査が行われ、審査に通ると補助金の採択通知がシステムに送られてきます。
事務局からの採択通知の後、事業申請者は速やかに交付申請を行います。交付申請の後、交付決定を受けることで補助事業実施が可能となります。
このように、ものづくり補助金は申請の手続きから採択結果の通知、補助事業内容の変更届や事業完了の実績報告、補助金の受給など全てのやり取りがインターネット上で行われるので、ネット回線やプリンター環境は整えておいた方がスムーズです。
GビズIDプライムアカウントの取得について詳しい内容はこちら
ものづくり補助金申請後のスケジュールは?
ではものづくり補助金の申請から補助金の受給に至るまでのスケジュールを、以下の第16次公募スケジュールを参考にしながら確認していきましょう。
*参考:https://portal.monodukuri-hojo.jp/schedule.html
まずものづくり補助金の申請者は、公募要領を見ながらどの補助金の枠で申請するかを決めます。
<補助事業実施前>
申請には、事業計画書やその他様々な必要書類があるので準備をし、GビズIDにてログイン後電子システムにて申請処理を行います。
その後提出した書類を基に補助金事務局が審査を行います。(審査の結果がでるまで大体2か月程度要します)
審査に通過すると「採択通知」が電子システムに届きます。しかしこの採択通知では補助金支払いが認められたということではなく、その後に行う「交付申請」によって具体的な補助金額が決定します。
交付申請では、実際に見積書や明細表等を確認しながら、事業者が行う補助事業内容の経費が補助金額として適切かどうか、ものづくり補助金の趣旨に沿っているかを細かく判断され「交付決定」となりようやく補助事業が実施できるのです。
*注意 交付決定が示される前の機材の発注や支払いにかかった経費は補助金の対象とならない点に留意しましょう。
<補助事業実施期間中>
いよいよ補助事業の開始です。事業者が注意しなければならないことは、ものづくり補助金の対象となる事業は、定められた事業実施期間内に、「発注・納品・検収・支払」等の全ての手続きを完了する必要があるという点です。
事業期間外の機械の発注や支払った経費はものづくり補助金の対象外となりますので、事業者は計画的に事業を進めていきましょう。
また補助事業実施期間中には、補助金事務局から「遂行状況報告書の提出や中間監査」が行われます。
<補助事業完了後>
補助事業が完了した後は、「実績報告書」及び見積書・請求書等などの経費出納帳関連書類・機材の納品場所写真等の提出です。電子システムから返送される書類の不備修正を行うとともに、事務局側からの「確定監査」を受け全ての書類が受理されると「補助金受給」となり、指定の口座に振り込まれます。
ものづくり補助金の補助事業期間は延長可能?
ものづくり補助金の補助事業期間は延長できるのか。
結論からいうと、ものづくり補助金の補助事業期間の延長は可能です。ただし、やや特殊な手順を踏む必要がありますので、以下に解説していきます。
ものづくり補助金の事業期間延長について
ものづくり補助金の事業期間は原則延長できない
ものづくり補助金の事業期間の延長は原則認められていません。
前述の通り、補助金の対象となる事業は、定められた事業実施期間内に、「発注・納品・検収・支払」等の全ての手続きを完了しなければならないからです。
事業期間内に納品されなかった設備機械や経費は全てものづくり補助金の対象外となります。そうなった場合の補助事業期間の延長は原則認められません。
事故等報告書によって例外的に延長可能
しかし、ものづくり補助金の補助事業期間の延長は原則できないのですが、やむを得ない状況に限り「事故等報告書」を提出し受理されることによって一定期間の補助事業期間の延長が例外的に可能になりました。
やむを得ない状況とは何かに関してですが、ものづくり補助金のよくあるご質問に事故等報告書の旨が記載されています。
Q28.採択を受けた補助事業が、予定された期間内に完了することが難しくなったときは、どの ように対応すればよいですか?
A28.大雨、台風などの異常気象による甚災地域の指定、火事・地震など事業者の責任によらない事由や予見可能性がない事由により補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その状況となった時点で速やかに「様式第4事故等報告書」を事務局に提出し、事務局の指示を受けてください。報告書の内容を確認の上、妥当と認められた場合は、一定期間の期限延長が認められます。個別具体的な状況を確認させていただきますが、電子部品の逼迫、国際物流の停滞、設備の納期遅延等もこれに該当し得ます。
つまり、事業者が予見できないやむを得ない状況(電子部品の逼迫、国際物流の停滞、設備の納期遅延)に限り、一定期間の事業期間の期限延長が認められるという内容です。
その状況に陥った場合、速やかに「様式第4事故等報告書」を補助金事務局に提出しましょう。
→「様式第4事故等報告書」はこちらからダウンロードできます。
参照:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付規程
事故等報告書の提出方法は?
事業期間の延長を申請する事故等報告書は、様式第4事故等報告書を作成した後、Jグランツから提出することができます。
Jグランツ内における事故等報告書の提出場所は、事業者が交付申請を行い「交付決定」の状態になると提出できる(クリックできる箇所が出現する)ようになります。
また事故等報告書の記述内容についてですが、
次の4点を記載します。
1.補助事業の進捗状況
2.事故等の内容及び原因
3.事故等に対して採った措置
4.補助事業の遂行及び完了予定
このうち、最も事務局が重要視しているのが 2.事故等の内容及び原因 です。この内容は、以下の交付規程にもあるように事業者の責任によらない理由は何なのかを説明する必要があります。
(事故等の報告) 第13条 補助事業者は、自己の責任によらない理由により、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに様式第4による事故等報告書を全国中央会に提出し、その指示を受けなければならない。
参照:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付規程
事故等報告書の記述方法で例を挙げると、海外の紛争や世界情勢による半導体の調達不安、木材価格高騰等による資材の納期遅延から製造メーカーが製品を調達できない事態となって事業の進捗が遅れているなどです。
他にも、新型コロナに感染し、作業員の濃厚接触者が増えたことで補助事業に遅延が生じているなど様々な状況があります。
事故等報告書には例に挙げたような内容を記述し、3.事故等に対して採った措置を説明した後、事業期間の完了日を記載します。
事故等報告書の提出によって、事業期間の延長が認められた場合、約3か月の期間延長が認められます。
事故等報告書の差戻しと再提出
注意点として、事故等報告書は申請したからといって全ての案件が認められることはなく、申請が通ったとしても内容不十分等の理由で、報告書の差し戻しが生じることもあります。
その場合は、報告書の内容を修正し、再提出を行うと事業期間の延長が認められる可能性がでてきます。 諦めずに報告書の差し戻しには対応していきましょう。
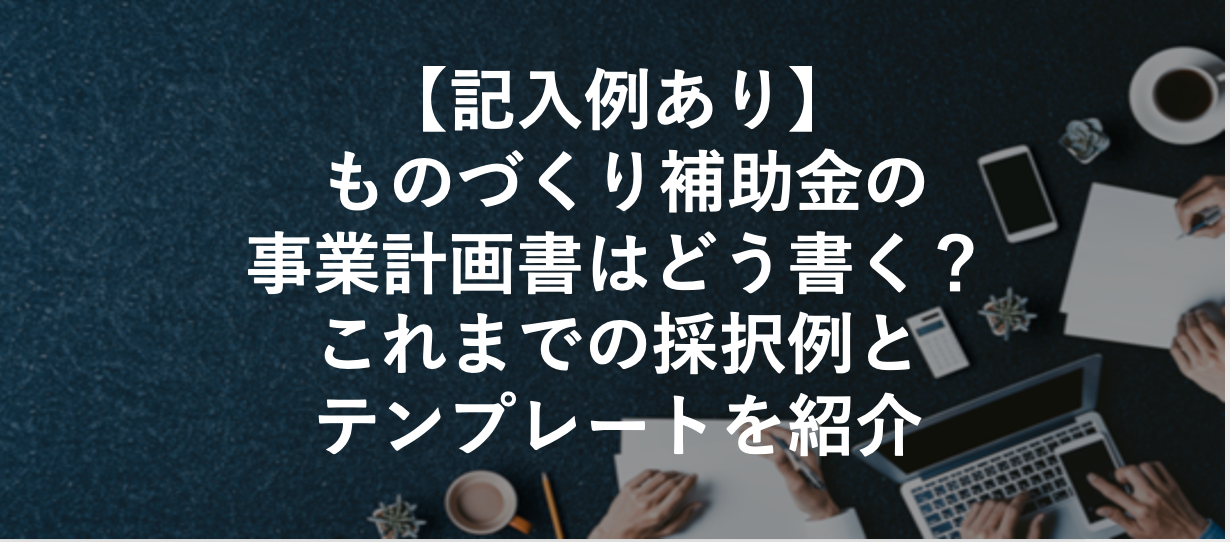
まとめ
今回はものづくり補助金の事業期間の延長が認められるかという内容でした。世界情勢や資材高騰などによる製造機器納品の遅れなど、事業者も補助金事務局も予見できないやむを得ない状況では事故等報告書の提出により、一定期間の補助事業期間の延長が認められます。
事業期間の延長は1度きりなので、延長申請を行った後は適切に期間内に事業を完了させるように注意しましょう。