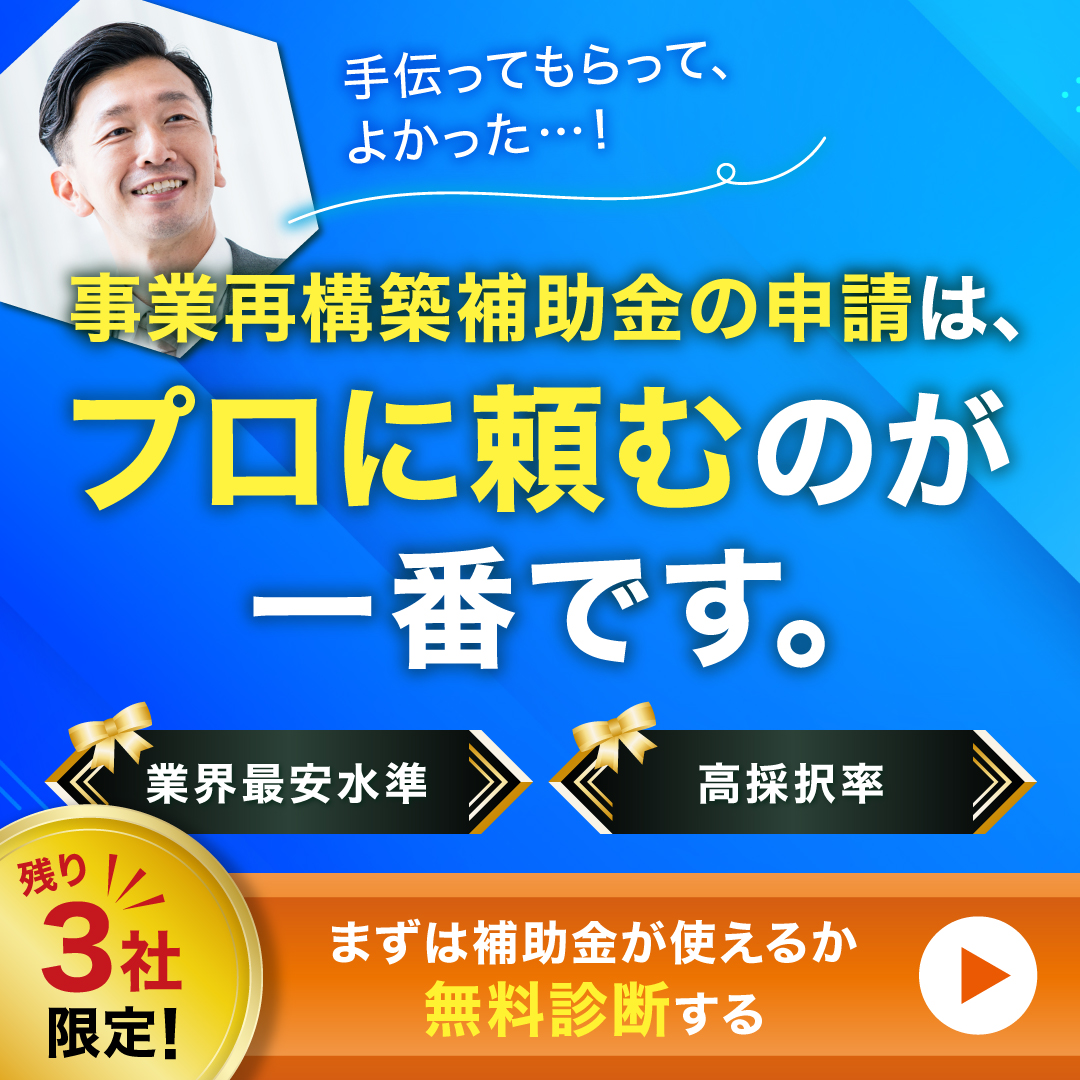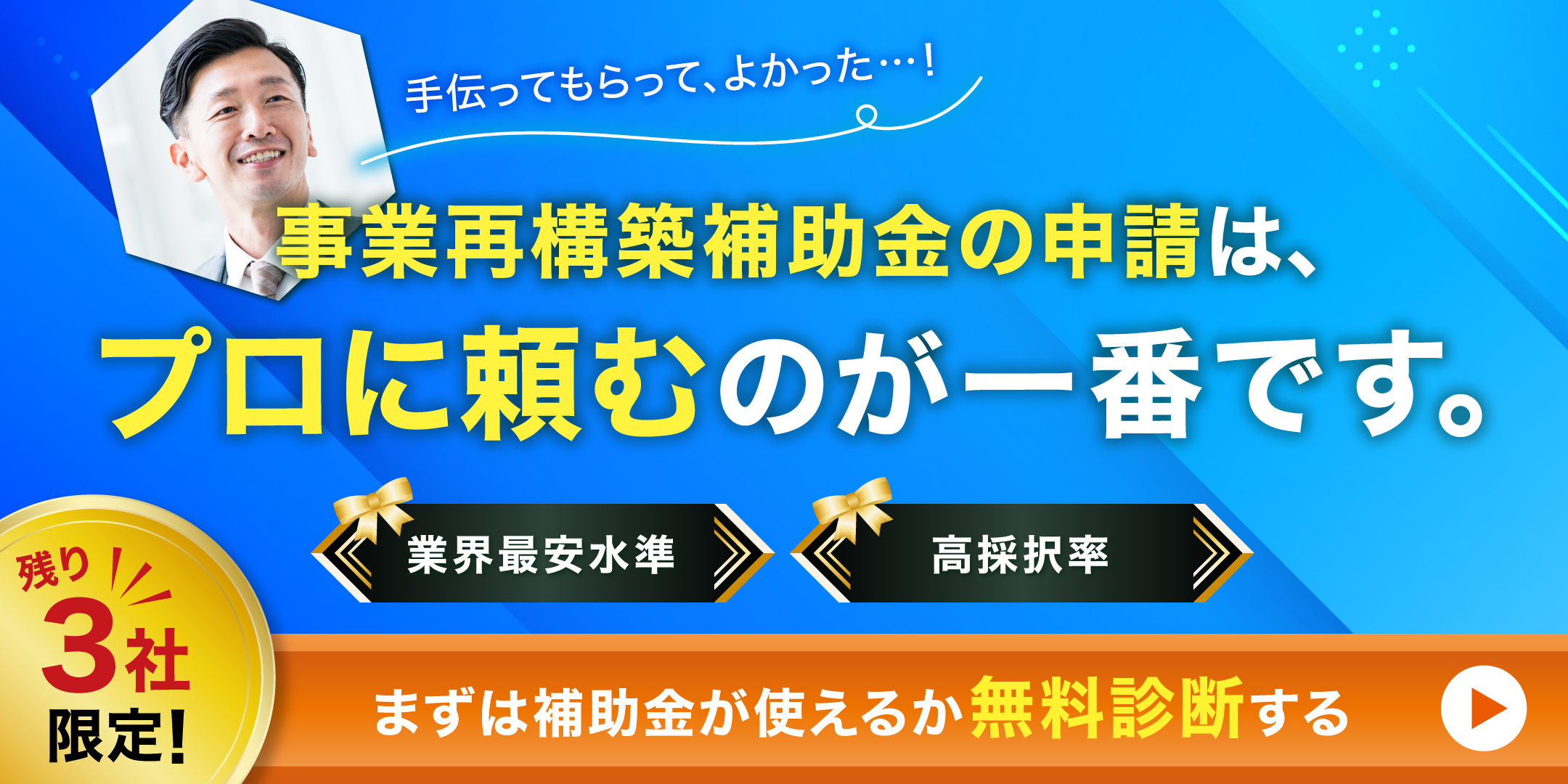【2024.2】事業再構築補助金の申請のための要件について徹底解説!
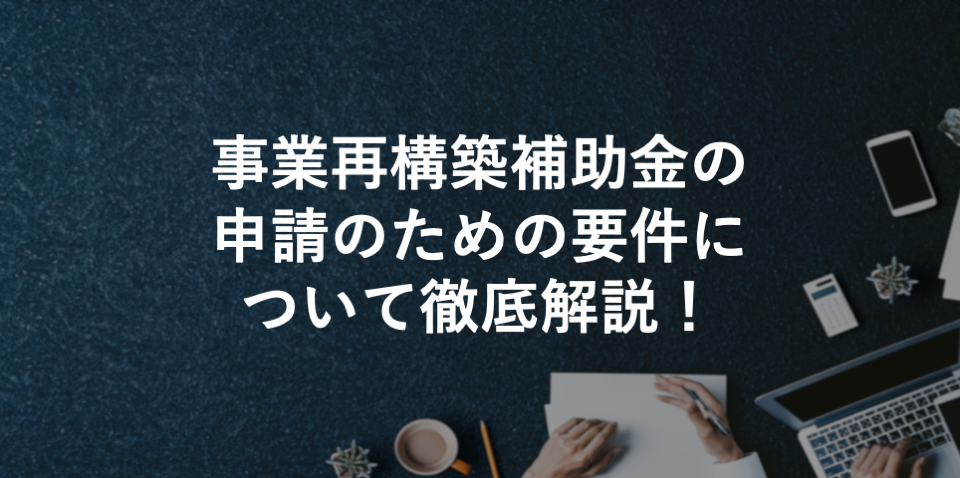
事業再構築補助金は要件に当てはまれば申請可能!この記事を読めば自社の状況が事業再構築補助金の要件に当てはまるのか判断することが出来ます。事業再構築補助金の公式サイトは少し難しい表現で記載されていることが多いので、ここではわかりやすく解説していきます。それでは、事業再構築補助金の要件からさっそく見ていきましょう。
事業再構築補助金の要件について

売上高等減少要件
事業再構築補助金の要件1つ目は売上高、付加価値減少要件です。中小企業庁の事業再構築補助金HPにはこう定められています。
「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも事業再構築補助金を申請可能。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。」
事業再構築補助金の要件は最初から難しい表現が並んでいますが、要は売上が減っているかどうかという要件です。ただし、単に売上が減っていれば売上高、付加価値減少要件に該当するわけではありません。売上高、付加価値減少要件には期間が定められています。
売上高、付加価値減少要件の期間とは2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることです。
ちょっとまだ難しいので例を出しましょう。例えば2021年1月から6月を選択したとして、その中で一番売上の低かった1月、3月、5月をピックアップします。この場合、2019年又は2020年の1月と3月、2019年5月の売上合計と比較を行い要件を満たすか判断します。
売上高、付加価値減少要件の期間は2020年4月以降で連続6ヵ月の中から3か月を選択し、それを2019年1月から2020年3月までの同じ月と比べれば良いということです。

事業再構築指針に沿った事業再構築の実施
事業再構築補助金の要件2つ目の要件である事業再構築指針に沿った事業再構築の実施もタイトルだけではわかりにくいでしょう。「事業再構築」に関しては、中小企業庁が事業再構築指針というものを定めています。事業再構築指針に沿っていれば要件に当てはまり事業再構築補助金を申請可能ということです。具体的な内容を以下で見ていきましょう。

事業再構築要件とは

要件2つ目の事業再構築要件とは、新規事業が満たすべき要件でありこの要件を満たさなければ事業再構築補助金は申請できません。事業再構築要件は5つの類型があり、各類型にいくつかの満たすべき項目があります。事業再構築要件を5つ、以下で出来る限りかみ砕いて説明します。
新分野展開
はじめに新分野展開について説明していきます。新分野展開は今まで提供していなかった新たな商品やサービスを提供することです。新分野展開を理解しておくと、他の事業再構築要件も理解しやすくなるでしょう。
新分野展開の定義は中小企業庁はこう定めています「新分野展開とは、中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が 属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同 じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定め る日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業をいう。以下同 じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービ スを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。 」
中小企業庁の定める新分野展開の定義は難しい表現が並んでいるのでここではかみ砕いて説明します。
新分野展開とは、例えば、航空部品を作っていた会社が医療機器部品を作ることにした場合が要件に該当します。他には、デイサービス事業を行っていた会社が病院向けの給食事業を開始した場合も要件に該当します。
新分野展開のポイントは、製造業やサービス業などの事業を変更せずに新しい製品やサービスを提供する点で要件を判断することにあるといえます。
事業転換
次は事業転換です。
定義はこうです「事業転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。 」
事業転換は新分野展開と似ているのですが、新しい製品やサービスが売上構成比の最も高い事業となる見込みである点で要件が異なります。先ほどの例でいえば、航空部品を作っていた会社が医療機器部品を作って売ったら航空部品よりも売れるようになった場合が要件に該当します。
新分野展開と事業転換の違いは少ないですが、売れ行きがどうなるかで新分野展開・事業転換に分類される点がポイントです。
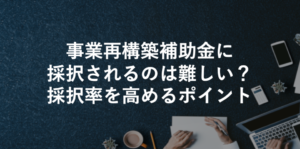
業種転換
業種転換の定義はこう定められています「業種転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。」
主たる業種とは、自社が行う最も売上のある業種のことを言います。ここで、業種とは日本標準産業分類という総務省が出している分類に従って要件に該当するか判断します。例えば、農業、建設業、運輸業、小売業などと分類されています。
要は業種転換とは、文字通り業種を変えてしまうことです。例えば、航空部品を作っていた会社がデイサービスを提供する場合が要件に該当します。新分野展開と業種転換との違いは、主たる業種を変えるか変えないかの違いです。
業態転換
業態転換の定義はこう定められています「業態転換とは、製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。」
業態転換とは、営業方法を変えてしまうことです。例えば、居酒屋を経営していた会社が弁当の宅配事業を新しく開始した場合が要件に該当します。また、対面販売していた紳士服店がネット販売に切り替えたり、レンタルに切り替えた場合も要件に該当します。ポイントは製品やサービスの提供方法を変える点にあります。
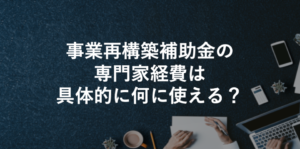
事業再編
いよいよラストの事業再構築要件です。定義はこう定められています「事業再編とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。」
すなわち事業再編とは、会社法に言う組織再編行為をして、上で見てきた新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のどれかを行うことです。会社法の組織再編行為とは具体的には、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡の事を言います。ポイントは、会社を切り売りしたり株式を売却して新しい事業を行う点にあります。

認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築補助金の要件3つ目は、認定経営革新等支援機関と事業計画を策定することです。「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業庁が認定した中小企業に対してサポートを行っていく機関のことを言います。専門知識があり、実務経験もある個人や法人が認定経営革新等支援機関として認定されているため安心して利用することが可能です。
なお申請する補助金額が3,000万円を超えるような場合には合わせて金融機関による確認書が必要となってきます。

どの事業再構築要件が活用できるかはプロと相談するのがおすすめ
事業再構築要件を説明しましたが、いかがだったでしょうか。事業再構築要件は複雑で、どの要件が該当するのか、活用できるのかを判断するにはかなりの時間を費やす必要があります。今回紹介した内容は事業再構築補助金の一部であり、より細かい事業再構築補助金の内容が中小企業庁の事業再構築補助金HPには記載されています。
これをイチから経営者の方が事業再構築補助金の全て読み解き、事業再構築補助金の要件に合うように経営計画を立てるのは効率的でしょうか。事業再構築補助金を申請するのに時間をかけて本業がおろそかになるようでは元も子もありません。
時間を削減し賢く事業再構築補助金を活用するためにはプロフェッショナルへの依頼を検討するとよいでしょう。事業再構築補助金の経験豊富なプロのコンサルタントを利用することで、どの事業再構築補助金の要件に該当し、どのように事業再構築補助金を申請すればいいか道筋をハッキリさせることが可能です。
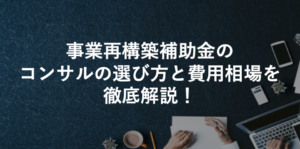
事業計画に反映させるためには丁寧なヒアリングが必要
事業再構築補助金の申請が通りやすくなる事業計画を、実際に事業再構築補助金の必要書類に反映させるには丁寧なヒアリングが必要です。
事業計画を何件も作成してきたプロの事業再構築補助金のコンサルタントに依頼することで、経営者の意図を事業計画に反映し事業再構築補助金申請をより確実なものとすることが可能です。事業再構築補助金の事業計画は経営者の意図を的確に反映させることが必要です。丁寧にヒアリングをしてくれる事業再構築補助金のコンサルタントを利用することは、企業の成長には欠かせません。
自社の成長に協力的なプロのコンサルタントを利用して、時間を削減し事業再構築補助金により事業の成長を目指してみてはいかがでしょうか。
おすすめの事業再構築補助金関連の記事も合わせてチェック
・直近公募回のスケジュール
・コンサルの選び方
・採択率の分析
・交付申請の方法
・事前着手の方法
・個人事業主の申請方法
・事業計画書の作成方法
まとめ
この記事では、事業再構築補助金を申請するために必要な要件について解説してきました。事業再構築補助金を活用することで初期費用を大幅に押さえて新規事業を始めることが可能です。今回紹介した要件に当てはまるか一度確認して、要件を満たせるようであれば、ぜひ申請を検討してみてくださいね。