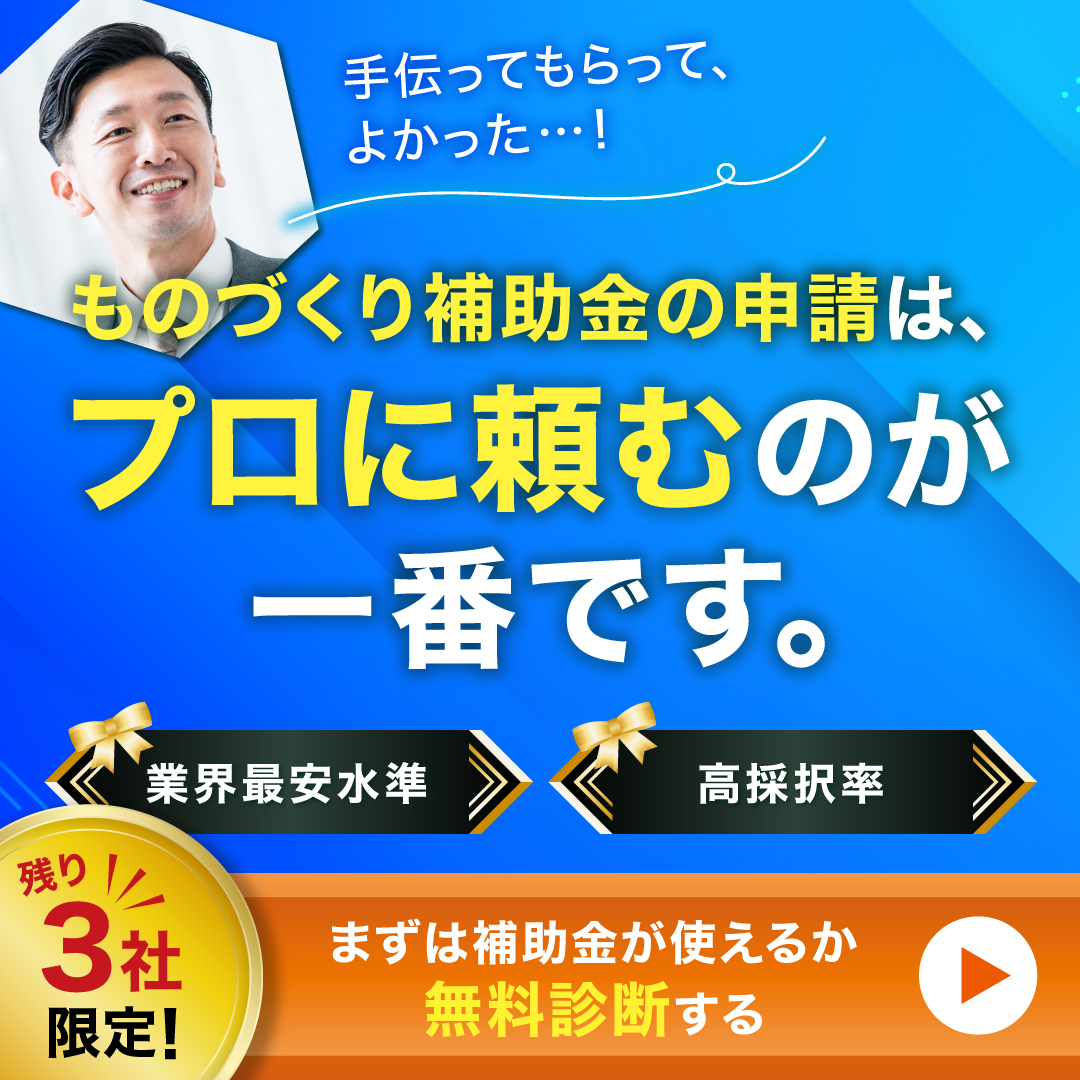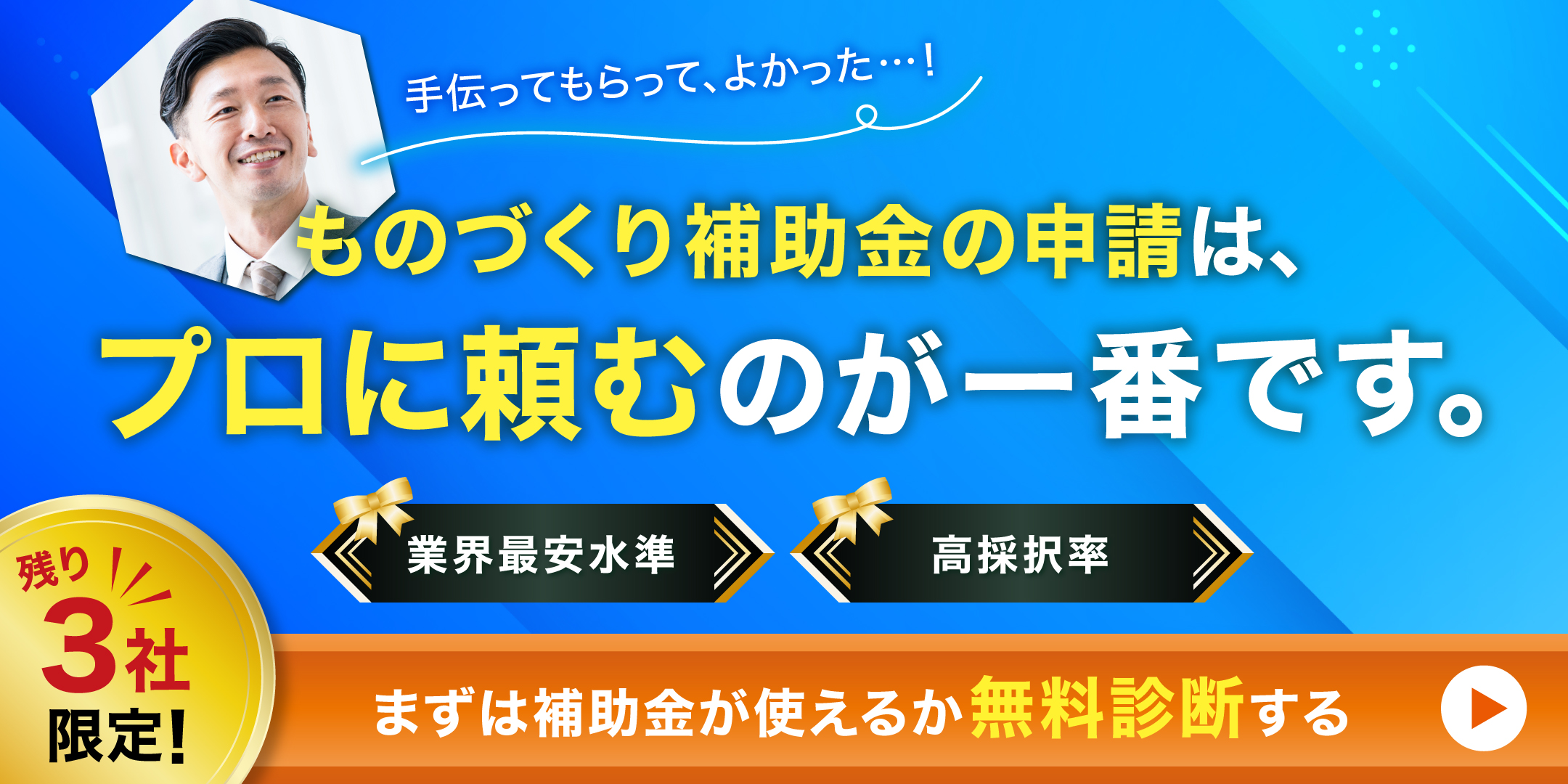【2024.3】ものづくり補助金は自動車整備業でも使える!実際の採択事例を4つ紹介
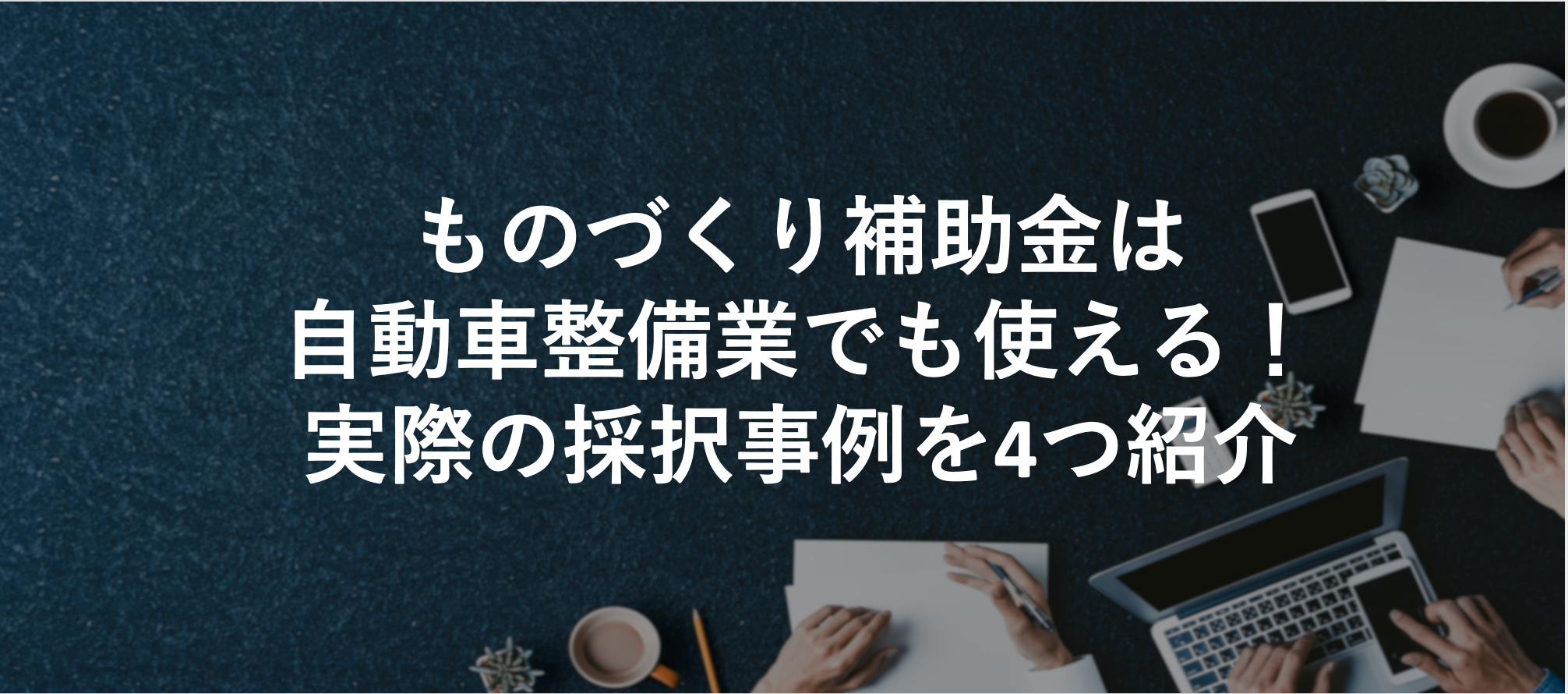
ものづくり補助金と聞くと、自動車整備業・自動車整備工場では利用できないと考えている方が多いのではないでしょうか。実は、自動車整備業でもものづくり補助金は利用できるのです。
自動車整備業・自動者整備工場は、設備投資や後継者育成など、事業の発展に向けて多くの課題を抱えています。そのため、自動車整備業におけるものづくり補助金の活用はさまざまなメリットがあります。
この記事では、自動車整備業のものづくり補助金の採択事例について解説していきます。
- ものづくり補助金の補助率・上限金額が分かる
- 自動車整備業のものづくり補助金活用事例が分かる
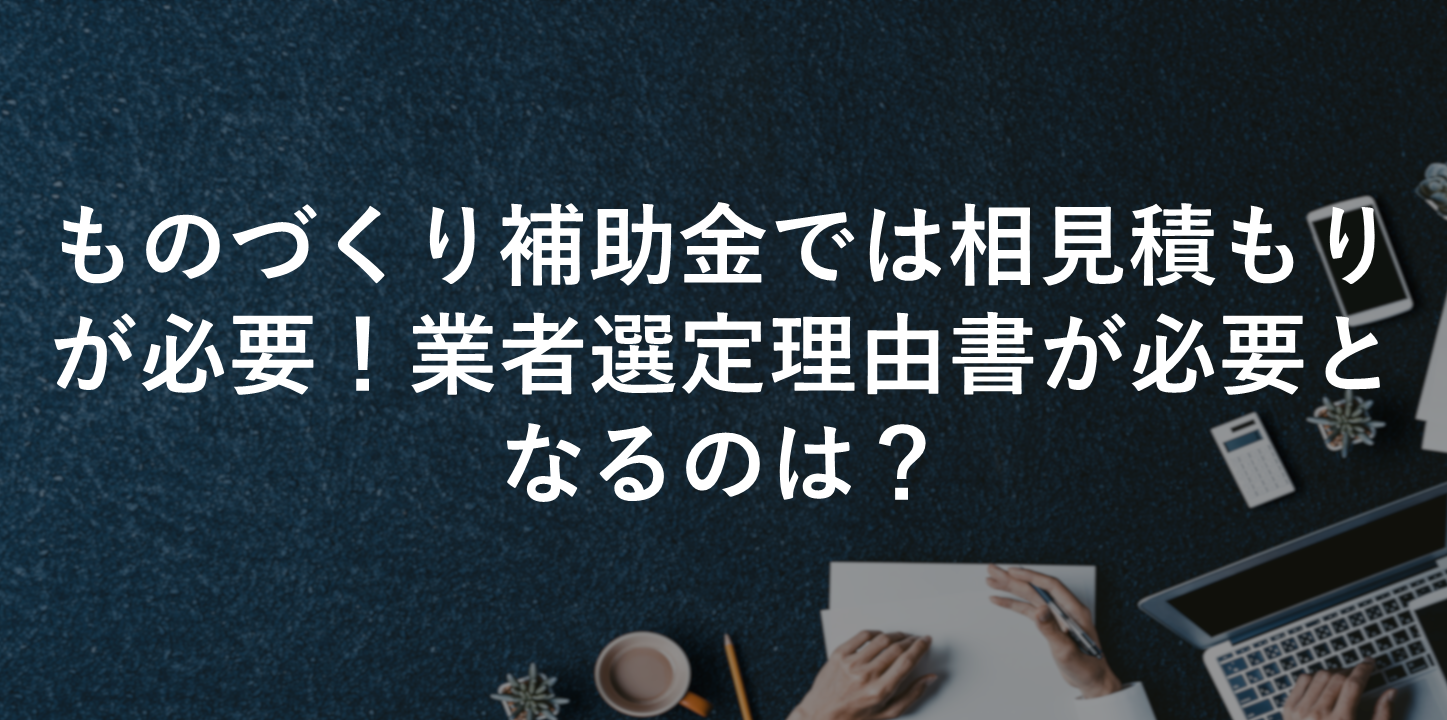
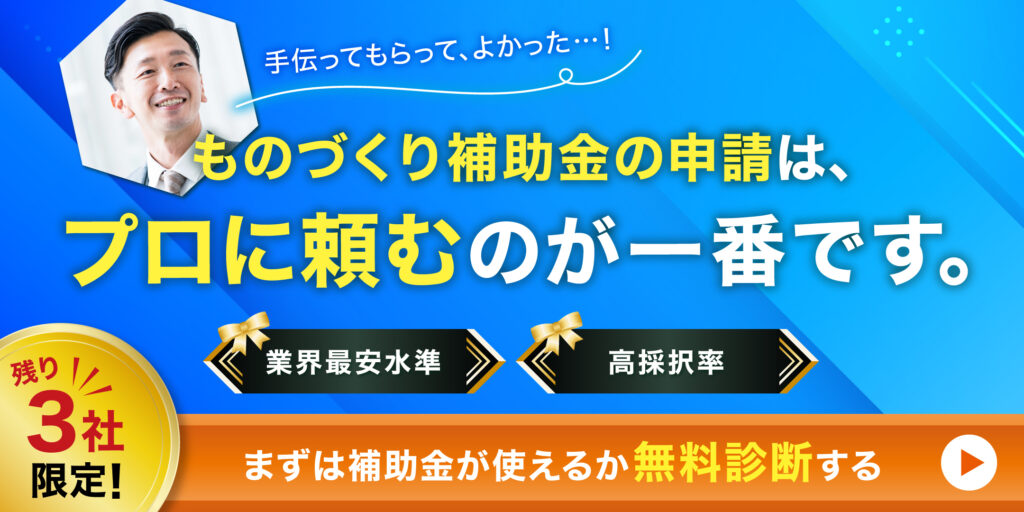
ものづくり補助金とは
ものづくり補助金とは、中小企業や小規模事業者がものづくりに取り組む際に、国が一部の経費を支援する制度です。この制度は、自動車整備業などの日本のものづくり産業が世界に通用するようになることや、地域の経済活動を活性化することを目的としています。
ものづくり補助金は、小規模事業者や中小企業、個人事業者にとって有効な支援策です。ものづくり補助金は、技術やサービスの品質や競争力を高めるために必要な設備投資に対して、国が一定の割合で費用を負担してくれます。
ものづくり補助金を利用する際は、資本金や従業員数などの基準をクリアする必要がありますが、これらの条件は比較的緩やかであり、自動車整備業など多くの事業者が応募できるようになっています。また、ものづくり補助金は法人だけでなく、個人事業主も対象です。自動車整備業を営んでいる事業者も、従業員等の要件を満たしていればものづくり補助金を受け取ることができます。
ものづくり補助金とは
ものづくり補助金の基本要件
ものづくり補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす3〜5年の事業計画を作成する必要があります。
基本要件
- 事業計画期間中に、給与支給総額を年率平均1.5%以上上昇させること。 (被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上上昇させること)
- 事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上に設定すること。
- 事業者全体の付加価値額を事業計画期間中に年率平均3%以上増加させること。
- 事業をおこなう法人であること
- 補助金交付申請時点で、従業員数が5人以上であること
- 賃上げ計画を実施すること
なお、補助金額は、従業員数に応じて異なります。これは、自動車整備業においても同様です。
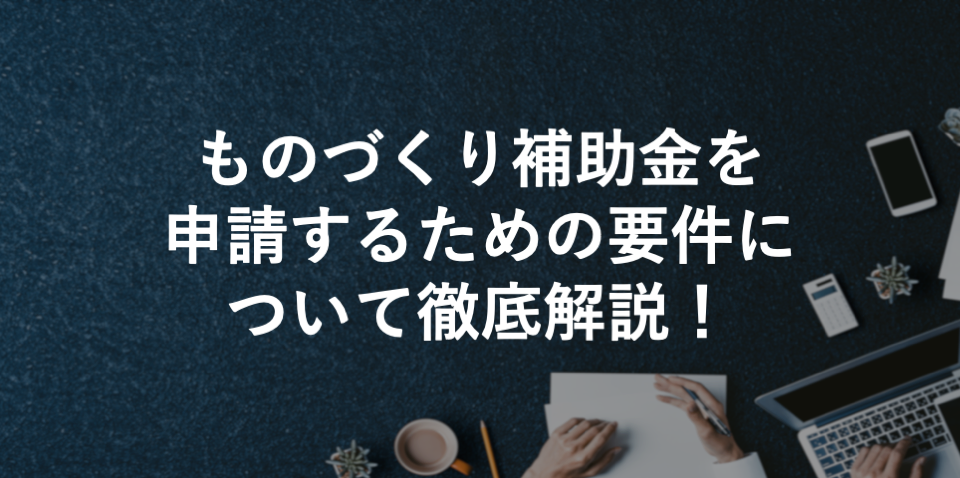
自動車整備業がものづくり補助金でもらえる金額と経費について
ものづくり補助金では実際いくら補助してもらえるのでしょうか。以下では具体的な金額や対象経費について解説します。
自動車整備業がものづくり補助金でもらえる金額と経費について
ものづくり補助金の補助金額と補助率
自動車整備業の事業者がものづくり補助金で受け取れる金額と補助率は、以下のとおりです。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | |
| 省力化枠 | 750万円~ 8,000万円 | 1/2 (小規模・再⽣事業者:2/3) | |
| 製品・サービス高付加価値枠 | 通常類型 | 750万円~ 1,250万円 | 1/2 (小規模・再⽣事業者:2/3) ※新型コロナ回復加速化特例:2/3 |
| 成長分野進出類型(DX・GX) | 1,000万円〜 2,500万円 | 1/2 (小規模・再⽣事業者:2/3) | |
| グローバル展開型 | 3,000万円 | 1/2 (小規模・再⽣事業者:2/3) | |
ものづくり補助金は、毎年公募されており、申請する事業や支援率、支援上限額などは公募要領によって異なります。ものづくり補助金を利用するためには、事前に必要な書類を準備し、指定された期間内に電子申請システムで申請する必要があります。申請枠ごとにも補助金額は異なります。
また、従業員数でも補助金額は異なるので、申請前に従業員数を確認しておきましょう。
ものづくり補助金の対象経費
ものづくり補助金における対象経費は以下の通りです。さまざまな対象経費があるので、どの経費が対象になるのかをしっかり確認しておくことが大切です。
対象経費
- 機械装置・システム導入費:事業のために必要な機械・システムなどに使った経費
- 技術導入費:事業のための知的財産権の導入にかかる経費
- 専門家経費:事業のために専門家の力を借りる際に発生する経費
- 運搬費:事業にかかわる運搬料、宅配・郵送に必要な経費
- クラウドサービス利用費:事業のために必要なクラウドサービス等の利用費
- 原材料費:事業における試作品の開発に必要な原材料等の購入に必要な経費
- 外注費:新製品やサービスの開発を行う場合に、必要な業務の一部を外注した際にかかる経費
- 知的財産権等関連経費:事業化にあたって、必要となる「知的財産権等取得に必要な弁理士の手続代行費用」や、「外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費」に該当する経費
自動車整備業においては新たな機械を設置するための機械装置・システム導入費や技術導入費等を使う方が多いのではないでしょうか。
また、対象外経費として主なものは以下の通りです。
対象外経費
- 広告費・販売促進費:SNS広告やウェブ広告、チラシなどの宣伝にかかる費用
- 中古品:価格が明確でない中古品にかかる費用
- 研修費:自社の従業員に対する研修にかかる費用
- 不動産費:土地や建物の購入や賃借にかかる費用
- 自動車関連費:自動車やバイクの購入やリース、燃料代などの交通関連の費用
- 再生可能エネルギー発電設備:太陽光発電や風力発電などの設備にかかる費用
- 建設費:新築や改築にかかる費用
- 汎用性の高い事務器具や家電:パソコンやプリンター、冷蔵庫などの一般的な器具や家電にかかる費用
- 自社の人件費:従業員や役員の給与や賞与、福利厚生にかかる費用
これらの経費は、ものづくり補助金の目的である「生産性向上」や「新規事業展開」に直接寄与しないと判断されるため、補助対象外となります。ものづくり補助金を活用する場合は、他にも補助対象外となる経費があります。公募要領をよく確認する事が重要です。

ものづくり補助金を活用した自動車整備業の4つの採択事例
以下では、実際にものづくり補助金に採択された自動車整備業の事例を紹介します。
ものづくり補助金を活用した自動車整備業の4つの採択事例
①故障箇所の特定に活用するオシロ機能付診断機の導入
事業計画名:ハイブリッド車専用のワンストップサービス整備工場の構築
企業名:東正自動車整備工場
自動車整備業における町工場でも十分整備できるように、ものづくり補助金を利用してハイブリッド車の故障診断を実施し、故障箇所の特定に活用するオシロ機能付診断機を導入した事例です。
ハイブリッド車は、エンジンとモーターの両方を搭載しており、車の制御系が非常に複雑になっているため、故障診断には専用の機器が必要でした。また、故障診断をディーラーに依頼する必要があるため外注費用や搬送時間がかかる問題、ディーラーで修理を依頼で修理費用も高くなるのが課題でした。
オシロ機能付診断機導入によって、自社で故障診断をおこなうことが可能になり、外注費用や搬送時間を削減することに成功したのです。また、修理も自社でおこなうことができるようになり、修理費用も安く済むようになりました。
②超高張力鋼板に対応したスポット溶接機導入
事業計画名:超高張力鋼板に対応したスポット溶接機導入により安全性向上と短納期化の実現
企業名:有限会社美寄車体
ものづくり補助金を利用して新型車に使われる超高張力鋼板の修理を可能にするため新型スポット溶接機を導入した自動車整備業の事例です。
2000年代に入るとハイブリットカーが急速に増え、新型車の骨格部材に使われる超高張力鋼板を溶接できるスポット溶接機が必要になりました。これまでは、手持ちの溶接機は電流不足のため、修理にはドリルやサンダー等を用いた別作業が必要になり作業の時間が増え納期の遅延などが課題となっていました。
新型スポット溶接機を導入により、直接溶接ができるため別作業は不要となり、作業時間も5分の1程度まで短縮し納期の遅延をなくすことに成功したのです。また、超高張力鋼板素材の強度を損なわずに修理できるため、安全性も向上しました。
③コンピューター調色システム導入による新サービス
事業計画名:コンピューター調色システム導入による新サービス(ブライトネスサービス)の展開
企業名:持丸自動車株式会社
ものづくり補助金を利用して、塗装技術の向上及び自動車整備業における他社企業に負けない店舗を目指すため、コンピューター調色システムを導入した自動車整備業の事例です。
板金塗装の作業では、調色が重要な工程であり、調色には、色の種類や難易度によって、多くの時間と労力がかかっていました。
複雑な色の場合は、色の見え方が角度によって変わるので、3人のスタッフが半日かけて細かくチェックし、部分的な傷の修理でも3日から1週間ほどかかってしまうことが課題となっていました。
コンピューター調色システムを導入によって、専用カメラとコンピューターでボディカラーを分析し、色の配合を瞬時に読み取ることで、塗料の調合にかかる時間と労力を大幅に削減するだけでなく、調色の精度と品質も向上させ、コンピューターは、カメラで撮影した色のデータをもとに、最適な塗料の配合比を計算し、自動的に調合することに成功したのです。
④環境にやさしい地域初の水性塗料対応ブース導入
事業計画名:環境にやさしい地域初の水性塗料対応ブース導入による未来型整備工場化事業
企業名:有限会社ムトウ自動車
ものづくり補助金を利用して、地球的環境問題になっているVOCの削減を目指し、水性塗料対応塗装乾燥ブースを導入した自動車整備業の事例です。
自動車の外装塗装は、事故などで損傷した車両の修理の際におこなわれることが多く、塗料に含まれる有機溶剤や重金属などの環境負荷成分は、大気汚染や地球温暖化の原因となるということが課題でした。
水性塗料対応塗装乾燥ブースを導入によって、水性塗装の塗装表面を乾燥させるための温風機能が高く、温度・湿度を最適に保つことができ、風量制御装置により塗装面に合わせた温風が出るため塗装の被膜が乾きやすくなり、水性塗装の品質向上と乾燥時間の短縮を図ることに成功したのです。
その他の事例
その他にも、以下のような自動車整備業の採択事例があります。
事業者名:株式会社東光自動車整備工場
事業計画名:留萌管内初導入!自動車車検時の完成検査デジタル化に伴う生産性向上事業
事業者名:有限会社光自動車整備工場
事業計画名:アライメント設備の導入により特定整備作業の生産性向上
事業者名:株式会社都賀自動車
事業計画名:未来の車の安全性を守る!デジタル機器を活用した安全かつ効率的な自動車整備事業
事業者名:株式会社望月自動車商会
事業計画名:法人顧客の獲得と大型サイズ車に対応した自動車整備体制の確立
事業者名:株式会社NEXT INNOVATION
事業計画名:先進安全自動車の普及に対応した、デジタル故障診断と電子制御装置整備を駆使した新たな自動車整備への挑戦
事業者名:三原自動車整備協業組合
事業計画名:自動車整備における大型自動車整備体制の強化
事業者名:DFGホールディングス株式会社
事業計画名:自動車整備の効率化により増加する需要の受け皿となるための体制を整備する
事業者名:株式会社KAZ-PROjECT
事業計画名:エーミングに特化した自動車整備サービスの開発
事業者名:トータルカーショップラッキー
事業計画名:次世代自動車整備機器のデジタル管理技術で高品位サービスの提供
事業者名:合同会社ガレージ商事
事業計画名:ドライアイス洗浄機導入による先進の自動車整備サービス提供事業
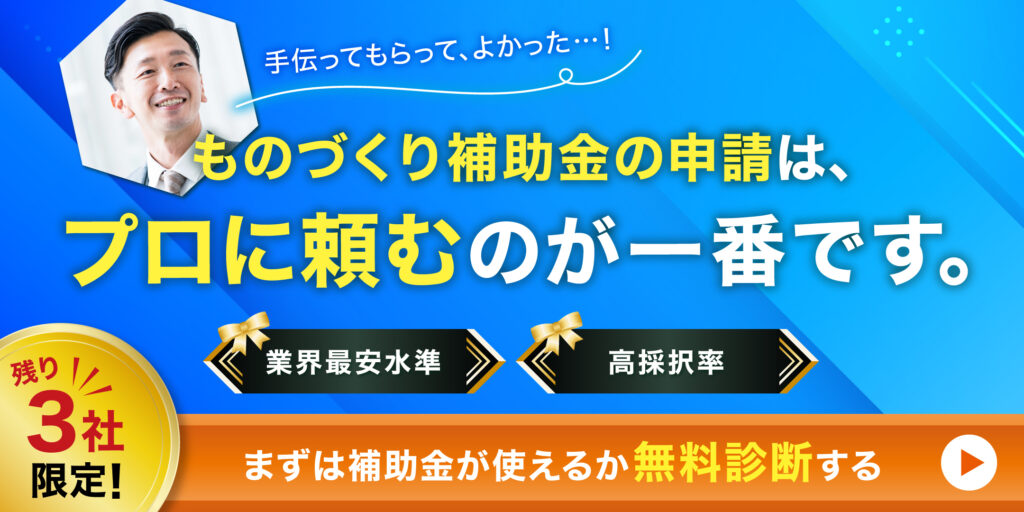
INU株式会社では自動車整備業のものづくり補助金申請を支援しています
INU株式会社では、ものづくり補助金の申請支援、コンサルを行っています。しっかりとしたヒアリングを行い、事業者様の強みを活かして言語化した事業計画書を作成します。これまでの採択率は90%と他社ではありえない高水準です。
システム関連にも強く、システム開発やシステム導入を目的としたものづくり補助金活用もお手伝い可能です。全国どこの事業者様でも、オンラインで対応が可能です。
初回のご相談は無料なので、まずは「自動車整備業だけどものづくり補助金が使えるか?」「採択されるにはどうすれば良いか?」などのお悩みをお持ちの方もぜひお気軽にご連絡ください。
ありがたいことに、現在多く事業者の方々から支援のご依頼を頂いております。定員に達し次第受付を締め切らせていただくので、ぜひ早めにご相談いただければ幸いです。
まとめ
この記事では、自動車整備業にものづくり補助金を活用する方法について解説しました。
自動車整備業は、設備投資や後継者育成など、事業の発展に向けて多くの課題を抱えています。自動車整備業にも適用されるものづくり補助金は、事業者の負担を軽減し、競争力を高めるための有効な支援策です。
自動車整備業でものづくり補助金の利用を検討している場合は、この記事を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。
以下の記事もチェックしてみてくださいね。